
宅建試験の合格点、実は特に決まっていないって知ってました?もちろん、合格者と不合格者が出ていますので存在はします。毎年変わるんで何点で合格とは一概に言えないのです。
ではどうやって合格かそうでないかを決めるのでしょうか。宅建の合格点の話、ちょっと考察してみました。
そして、その合格ラインを超えるために受験生はdプすべきなのか、解説してみましたので、興味あればどうぞお付き合いください。
宅建資格はかなりの人気資格ゆえ、本当にたくさんの通信講座が存在します。特に初心者の方は、その中から「どの通信講座を選べばいいかわからない…」という事態に陥るでしょう。 そこで2024年度試験に向けて、管理人が、オンライン …
宅建の合格点は35.3点!
宅建の合格点ですが、最新の令和6年度だと37点、直近10年間の宅建合格点平均は35.3点。宅建は1問1点の50問出題ですので、計算もシンプルで良いです。
直近10年でいえば、合格点が最も低いのが平成27年の31点、最も高いのが令和2年度10月開催分の38点です。
※令和2年度3年度はコロナの影響で2回開催で実施されていました。
100点満点に換算しますと70点強が合格点となりますが、これは資格試験としては高め安定していると言えるでしょう。平均とはいえ、70点取っても合格に足りないとはいかにも高いです。
宅建合格点の推移
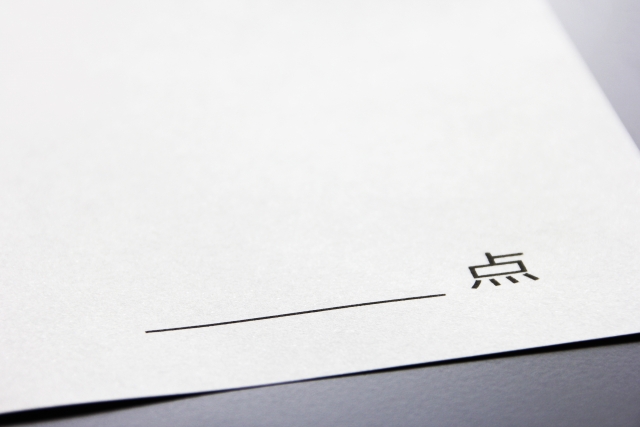 実際の合格点の推移を確認してみましょう。最新の令和6年度試験までの直近10年間の宅建試験の合格点の推移をまとめました、合格率と共にご覧ください。
実際の合格点の推移を確認してみましょう。最新の令和6年度試験までの直近10年間の宅建試験の合格点の推移をまとめました、合格率と共にご覧ください。
前述しましたが、令和2年3年はコロナ過の影響で1回の試験を2回に分けています。
| 年度 | 合格点(基準点) | 合格率 |
|---|---|---|
| 平成27年 | 31点 | 15.4% |
| 平成28年 | 35点 | 15.4% |
| 平成29年 | 35点 | 15.5% |
| 平成30年 | 37点 | 15.5% |
| 令和元年 | 35点 | 16.9% |
| 令和2年10月/12月 | 38点/36点 | 17.6%/13.1% |
| 令和3年10月/12月 | 34点/34点 | 17.9%/15.6% |
| 令和4年 | 36点 | 17.0% |
| 令和5年 | 36点 | 17.2% |
| 令和6年 | 37点 | 18.6% |
このように年度によって推移する合格点のことを基準点と呼びます。この基準点を満たせば合格、それ以下では不合格ということになります。この基準点の10年平均が35.5点であるのはその通りなのですが、推移を見て気づきがあります。
それは基準点が上昇傾向にあること。繰り返しますが、基準点直近10年間平均は35.3点です。でも、令和4年度以降は35.3点取っても合格はできません。
宅建合格点高すぎ問題について
以前は「7割(35点)正解すれば合格できる」という目安がありましたが、ここ数年は様相が変わってきています。「7割正解しても合格できない宅建試験」になってきています。要は点数とらないと合格できない試験になりました。
合格率も上昇傾向ですので、点数とる人の比率は高くなっているということですが、問題が簡易化しているということもありません、要は点数取る人の比率が増えているといえます。受験生のレベルは相対的に上がっていると言えます。
これから受験する方はこうした状況の中で上位17%の人間にならなければなりません。
宅建の合格基準点の決め方
 ところで、この合格基準点は毎年どのように決めているのでしょうか。公表はされていません。あくまで考察レベルですが合格基準点の決め方をお話したいと思います。
ところで、この合格基準点は毎年どのように決めているのでしょうか。公表はされていません。あくまで考察レベルですが合格基準点の決め方をお話したいと思います。
合格率を基準に問題を作成?
注目してもらいたいのが合格率です。基準点と一緒に掲載したのはこのためで、この合格率を毎年合わせるために問題を作成し、その結果基準点が毎年推移しているのではないかということ。
合格率は15~18%で収まっていますが、問題制作側はこの枠内で収まるように問題を作成しているのではないでしょうか。合格率を基準に考えれば毎年線を引く点は変わりますのでそこが合格基準点ということになります。
合格点決定のプロセスとは
合格点決定のプロセスはこう考えます。 受験者数は事前に概ねはわかっているので、合格率に合わせた合格者数は算出できます。
そこに想定した合格者数が出るようなレベルの問題を作成し試験実施。すると、受験者得点のランキングが出ますので、合格者15~18%で収まる点数のところに線を引く。そこが合格基準点になるというわけです。
受験生のレベルその他条件により毎年合格基準点は変動しますが、基本的には大きな差は出ません。それは原則として問題レベルを一定にしているからです。 以上をチャートにして下にまとめてみました。
- 合格率が15~18%に収まることが前提
- それには問題レベルを一定にすること
- 試験が実施され受験生のランキングができる
- 合格率15~18%に収まるところに合格基準点の線引き
宅建は類似問題が繰り返し出題
合格率で合わせるために問題作るなんてできるのかと言えばある程度は可能だと思います。 宅建試験は似たような問題が繰り返し出題されます。ちょっとはカスタマイズされますが、同じ箇所を同レベルで理解していれば解けるような問題が良く出題されるのです。
年ごとの受験生レベルの違いや類似問題ばかり出題されるわけではありません。受験生レベルが高ければ38点なんて年もありますしそうでなければ31点という年もあるわけです。
宅建は相対評価
ちなみに、合格点があらかじめ決まっておらず、試験の結果によって合格点が変動することを相対評価といいます。つまり、その受験生が実際に獲得した点数よりも、周りの受験生との相対的な評価で合否が決まるということ。
選抜試験はこの相対評価が一般的だと思います。この相対評価という概念が導入されているのは、何も宅建試験だけではありません。司法書士試験や予備試験などもそうです。
行政書士試験は絶対評価
逆に、周りの受験生の点数など関係なく、その受験生が獲得した点数でのみ合否が決まる国家試験もあります。これを絶対評価といいますが、行政書士試験はそうです。→参照:行政書士の足切り
今後宅建試験の合格点はどうなる?
では、令和7年度以降の宅建試験の合格点はどうなるか?というより、試験機関はどう考えているか考察してみます。ここ数年、基準点が36、7点ですので、ここを目安に考えるのが自然でしょう。
もしかしたら、問題難易度を若干上げてくるかもしれません、これ以上基準点を上げないために。
宅建試験で合格点を取るための対策とは
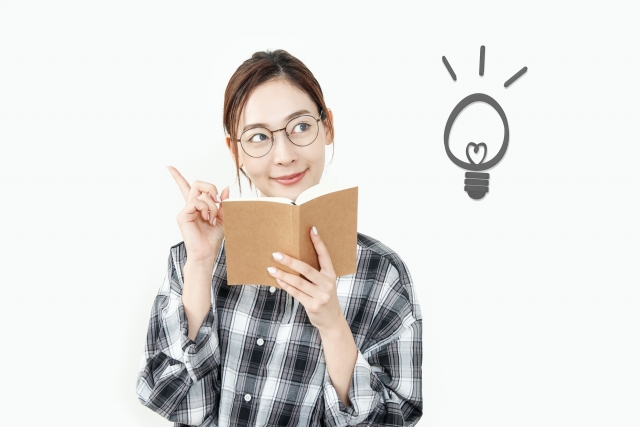 難問化があれば数年はそれを踏襲するでしょう。受験生はどう対応すればいいのでしょうか。個人的に3点あるのかなと思っています。
難問化があれば数年はそれを踏襲するでしょう。受験生はどう対応すればいいのでしょうか。個人的に3点あるのかなと思っています。
- 過去問アウトプット
- 権利関係を得意科目に
- 合格目標点を立てる
それぞれ解説していきます。
過去問アウトプット
宅建の合格点を獲得するためにもっとも効果的な勉強は、それは過去問の攻略だと思います。ここは変わりません。宅建は類似問題が頻繁に出題される試験ですので、過去問をしっかりつぶしておくことが何よりも大事なのです。 過去問とテキストをパラレルに連携して知識をまとめておくことが重要になります。
そうしておくことによって、試験レベルがわかりますし、出題傾向や重要箇所もわかります。
権利関係を得意科目に
科目攻略において、多くの方の最大の懸念は「権利関係」だと思いますが、その権利関係を得意科目にしましょう。 個人的推測ですが、問題の難問化=権利関係の難問化と読んでいます。
もともと権利関係という科目、宅建受験生には難しいとされ捨てても良いかとの声も上がるほど毛嫌いされています。 あまり点数は取れないと踏んでいる受験生が多い中、是非得意科目になって他受験生よりも多く得点できるようになってください。間違いなく他受験生と差が出るのはこの科目です。 権利関係の中心法令が民法です。
「民法を制す者は〇〇を制す」とある通り、きっと合否を左右する科目となり得るでしょう。
合格目標点を立てる
大雑把に「50問中35点!」を漠然とした目標ではなく、科目ごとに目標を立てると良いと思います。どの科目を重視すべきかが見えてきますし、目標は明確な方が良いです。
そもそも、科目ごとの難易度が異なるし問題数も違います。科目ごとに目標を定めた方が効率的だと思います。 ポイントは少し大きめに立てること。
| 科目 | 出題数 | 目標点数 |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20 | 17 |
| 権利関係 | 14 | 10 |
| 法令上の制限 | 8 | 6 |
| 税 | 2 | 1 |
| 土地建物、鑑定評価、需給関係 | (合わせて)6 | (合わせて)4 |
| 合計 | 50 | 38 |
まとめ
いかがでしょうか。宅建の合格点の決め方、無粋な言い方すれば「大人の事情」で決められているのだと察します。 いずれにしまして受験生はしっかり対策をして合格を勝ち取るだけです。それには第一には過去問です。宅建の出題性質を鑑みれば必須中の必須事項です。しっかりした対策を取って是非合格点を勝ち取っていただきたいと思います。

